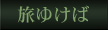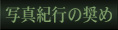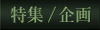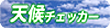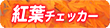2025.04.27 鷲子山上神社(その2)
■ 県境へ

そのまま r293 を進むとやがて那須烏山市の領域に至る。この付近も丘陵地ではあるのだが、那須烏山市のr293は樹林地帯を通るので視界は開けない。

とはいえ道端にはところどころ菜の花や花大根が咲いていて春の風情は感じられる。

視界が開けないうちに那珂川町の領域に入った。
菜の花のない那珂川の風景の話

やがてR294と交差して那珂川を渡る。 ここの景色は面白いのでちょっと語ってみよう。

何が面白いのかというと、那珂川の河川敷には渡良瀬川や利根川のような菜の花でいっぱいの景観はないのである。
※この写真は帰路に撮ったものなので光線具合が変わってしまっているけれども、まあ気にしないで頂きたい(笑)

ちなみにこちら(↑)は群馬県と栃木県の県境を流れる渡良瀬川の河川敷だが、もうそこらじゅうが菜の花で溢れている。利根川や荒川の河川敷も似たようなもので、3月~4月には黄色い絨毯のようになる。那珂川の殺風景な(?)景観と比べるととても対照的だ。

実はこれにはいくらか事情がある。
菜種油の原料となるアブラナはもともと温暖な関西が主要産地だった。これが江戸時代になって人口の急増する江戸で油の需要が増え、幕府は関東での現地生産を奨励した。 用途は食用油というよりは燈明で、当時は行燈(あんどん)や灯篭(とうろう)で燃やす燃料が不足していたらしい。
とはいえ江戸時代の経済は "コメの生産が最優先" の世相で、条件の良い土地はみな水田となっていた。 そこで目を付けられたのが低開発地の河原や土手で、これらが即席の菜の花畑として活用されたのである。 その置き土産が、現在野生化して利根川水系や渡良瀬水系に繁茂する菜の花という次第だ。

しかし江戸から離れた那珂川上流域では、河原での菜種油の生産は行われなかった。 実は関東で菜の花の河川敷がみられるのはほぼ徳川領の範囲と一致していて、那珂川も水戸藩領(徳川御三家のひとつ)に入ると菜の花の河川敷がみられる。
実はこれは菜種油の株仲間(商人の同業組合)と徳川幕府のコラボによるものだったらしい。 彼らは幕府公認で江戸市中への油の供給を独占的に請け負い、その供給元を徳川領内に優先的に割り当ててキックバックすることで、一種のカルテルを形成したようなのである。

こういう商人による統制経済は、戦国末期の織田信長の楽市楽座政策によって商人の組合である「座」 の廃止という形で消滅した筈であった。しかし徳川政権の時代になって、座は 「株仲間」 と名前を変えて事実上の復活を遂げている。 それが菜の花の有無というかたちで風景に影響しているのは、なんとも興味深い。
…おっといけない、本日は風景を眺める旅の筈なのに寄り道が過ぎた。 経済史の探偵ごっこ(笑)はほどほどにして、先を急ぐことにしよう。
■ 県境、そして神域の入口へ

那珂川を渡って馬頭の市街地を抜けると、ふたたび山また山の風景が展開する。ここはもう八溝山地の一帯で、標高200~400mくらいの起伏が続いていく。

やがて本日の目標地である鷲子山神社の案内板が出現した。ただしここは出口であって、入口はもう少し先、県境の向こう側にある。

状況を説明するとこんな(↑)感じになる。参道の入口が茨城県側になっているのは、かつてこの山に登る一の鳥居が茨城県側にあり、鷲子という地名も鳥居からさらに南方3kmくらいのところにあることによるのだろう。この神社の正面玄関は、茨城県側に向いているのだ。

県境を越えてしばらく行くと、いよいよ鷲子山入口の標識がみえてくる。

参道の起点となるここには10軒に満たない小集落がある。おそらくここが門前町にあたるのだろう。集落名は鳥居土という。参道は集落を貫通する緒川という沢に添って伸びている。

そこから先はひたすらこの細道を登っていく。 平安時代からつづく峠道で、昔はここが常陸国~下野国の国境越えの道であった。
所々に待避所はあるものの、道幅は3mほどしかなく基本的に対向車が来たらアウトという状況だ。 一方通行にしてあるのは致し方ないところだろうな。

3kmほど参道を登っていくと、神社の境内に到着する。クルマで来るとたいしたことのない道に思えるが、標高差は200mほどあるので徒歩で上るとちょっとした有酸素運動になりそうだ。

神社の境内は狭いのでクルマを停めるのは150mほど先の尾根の鞍部になる。道路の左側は切り立った崖になっていて、道はとにかく狭い。

駐車場はさすがに斜面そのままではなくある程度整地されていた。とはいえせいぜい30台も停めたら一杯になってしまいそうだ。 峠の山頂だけにキャパシティはほとんどない。結構大変な立地なのだなぁ。
<つづく>